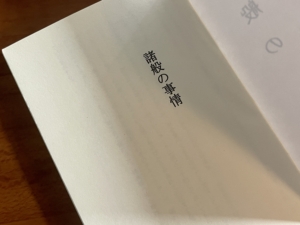夫に勧められて、貸してもらって読んだ。どうしようもない気持ちになるけれど、面白いよ、と。
村上龍を読むのは何年ぶりだろう?
たしかに面白い。
断定口調の短文が読点で連なってゆく文体は、スピード感と重みを同時に伴い、有無を言わさぬ強さを持つ。
しかしながらはじめのうちは、
「登場人物のうちの誰にも感情移入できない小説だなあ……」
そういう違和感があった。
それが、上巻を終えて下巻に入る頃には、
「わたしにとって共感できる登場人物が存在しない、ということではない」
「わたしの中にすべての登場人物が存在するのだ! だからある特定のひとりに感情移入することができなかったのだ」
と気がついた。
つまり登場人物たちは物語の中というよりもむしろ、読み手である「わたし」というひとつの主体の内側にいて、結託を目指し、分裂し、憎み合い、殺し合っているように感じる。
そして、物語が進むに連れてじわじわと、わたしという主体がただひとつの質感にまとめられてしまうような感覚を覚える。
小学校の図工の時間、パレットにある絵の具をすべて混ぜてみたあの感覚!
この小説を読んでいるときに感じる粘っこい不快感の正体はこれだ。
はじめは多彩だったはずの内的世界で、複数の色の輪郭が互いに溶け出し、曖昧なマーブル模様が生まれてから徐々に一色の暗い色になる。
そうして最後のページに辿り着いたとき、
なんということだろう!
一瞬だけ輝く鮮やかな色があるのだ。
自分にとって、フィクションを読むということの意義を感じさせる作品であった。
0