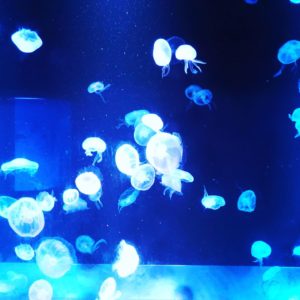アイロンを掛けていた。
彼のシャツに、彼自身が選んだアイロンを使って。
今わたしが使っているこのアイロンはとても重たい。その重み自体で、しわが伸ばされてゆく。
なんとも言えない、とても心地よい感覚だ。
アイロンというのは同じ機能であれば、重みがあるほど高価であるように思う。
これを買った当時学生であったわたしたちに、この重いアイロンは決して安くない値段で、しかもそのときのわたしにはアイロンの重みの大切さがわかっておらず、でも、当時アイロンがけを担当していた彼がどうしてもこれがいいと言ったので、それならと選んだことを覚えている。
アイロンがけがわたしの仕事になった今、あのときの彼の意見が正しかったのだとようやくわかる。
この重たさのおかげで、今わたしはこうしてアイロンを掛けながら考え事ができているのだ。
ほとんどをアイロンがやってくれて、わたしはただ手を添えているだけで良いから。
なるほどこれが投資の精神か、と思って感心する。
しかしその瞬間に「それを言うなら、アイロンのいらないシャツを買うべきなのか?」という声が頭の中に聞こえる。
少しびくっとする。
そうやってひたすらに考え続けると、生きることをやめるべきというところにたどりついてしまわないだろうか?
ついこの間、わたしたちのふたりともが疲れ果てていた休日、気分転換にと、ちょっとだけ近所をお散歩することになった。
あてもなく歩いているとなんだか楽しくなってきて、案外遠くまで歩き、せっかくだからと、ずっと気になっていたカレー屋さんに行ってお昼にすることにした。
そのとき、彼は少しカジュアルな、デートのときにはあまり着ることのないシャツを着ていた。
まさかコートを脱ぐとは思っていなかったのだ、と少し照れながら弁明をしていた――その光景を今、まさにそのシャツにアイロンを掛けながら突然、鮮明に思い出した。
そして、
ランチの時間から少し外れてガラガラだった店内、
メニュー表のフォントと色、
ネパール人と思われるスタッフの人達の声、
レジ台に貼ってあった手書きの「ネパール語こうざ」。
脳裏に蘇る何もかもがあたたかく、くすぐったく、淡く、やわらかく、脆くて、わたしは怖くなる。
終着点、あるいは境目を探し続けるわたしの癖を思う。
一本のロープをたどるように、ある物事の延長線を探り続けるような。
その癖を発揮していると、いつもある一定のところで視界に靄がかかったようになり、それ以上進むことに対して抵抗が発生する。
そこには結び目でもロープの終わりでもなく、そもそも何かがあるのか、何もないのかということもわからない。
その不思議な空間で、ただ自分の手のひらにロープが当たっているような感覚だけがあるのだけれども、それも次第に薄れてゆくような気がする。
あれは、あの靄は、ぜひとも突破すべきものだとずっと思っていた。
けれども今わかった。あれはサインなのだ。
そこでは、がむしゃらに前進すべきではない。いったん考えるべきポイントが訪れたよと、そう知らせる靄なのだ。
そこでやるべきなのは、一番はじめの頃、何のためにそのロープを掴んだのかを思い出すこと。ただそれだけでいいのか。なあんだ……
そんなことを考えていたら、いつの間にかすべてのシャツのしわが伸ばされていた。
手のひらにふたたび感覚が戻ったので、わたしはアイロンを掴んで持ち上げ、もとの場所に戻した。