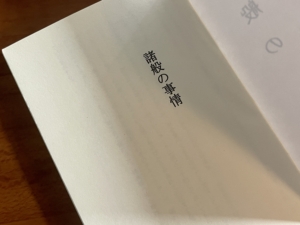スピンクシリーズの最終巻。
このシリーズは、スタンダードプードルのスピンクによる一人称で語られる。
スピンクは犬なので自分で文字を書くことはできない。
そこで、主人公・ポチ(=町田康?)の脳に直接語りかけることによってこのシリーズを執筆しているのだ。
スピンクという犬は実際に町田康と共に暮らしていて、2017年6月27日にこの世を去った。
▼町田康による鎮魂歌もある。
本の最後に語り手自身が亡くなってしまう、そしてそれが現実のことであるというのをわたしは読む前に知っていた。
その上でこれを読み始めるのはやはりつらい。
そういうわけで、買って以来なかなか手を付けられず積んであったのだが、ようやく今月読むことができた。
これまでのスピンクシリーズ(『スピンク日記』『スピンク合財帳』『スピンクの壺』)を通して、わたしたち読者が長く親しんできたスピンクのあの文体。
最終章はついに、それではない、別の語り口で綴られる。
その口調は、取り乱すことなく、優しく丁寧であり、それでいてそこはかとなく寂しく、スピンクへの気持ちが言葉の端々に滲み出るようなもので、わたしはどうがんばっても泣くのを堪えられなかった。
誰かの死に際してわたしたちには大きな悲しみが訪れる。
それは死者自身に対してではなく、遺された自分や誰かに向けられた悲しみだ。
親しい者の死自体ではなく、それによってもたらされた、自分たちのこの現実が悲しいのだ。
そしてその悲しみは、いつも穴の形をしている。
誰か近い人が死んだとき、自分の身体や、自分の部屋や、見慣れた景色に穴が開くのをわたしは感じる。
昨日まであったものが今日はそこにない、そういう種類の穴。
「スピンクがいなくなって、家の中が静かです」
帯に採用されたこの一文が、それをいちばんよく表している。
今回スピンクという、一度も直接会ったことのない犬が死んで、久しぶりにその穴が自分の真ん中にぽっかりと現れた。
そういう穴は、誰かが死んだら必ずいつもあく。
けれども、それを通して自分の中に吹き込んでくる風の温度や質感は、不思議なことに死者によって異なる。
この本の読後わたしの中には、驚くほど穏やかなパステルカラーの風が吹いた。
死者に花を手向けたくなる気持ちが、自然に生じたのははじめてのことだった。
まっすぐに立つ、茎の細い、一輪の黄色い野花がいい。
あのピンク色の耳と飄々とした性格に、それがとても似合う気がした。
▼参考:その他のスピンクシリーズ