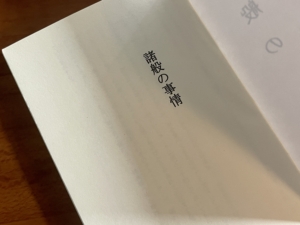少し前のニュース。
出生数90万人割れへ 19年、推計より2年早く:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50672490W9A001C1MM8000/
まだ90万人も生まれていること、生まれさせることを決めた親が90万組もいることにむしろ驚愕する。わたしはそっち側の人間である。
川上未映子の本だけがわたしの理解者だった
幼い頃から、人間が人間を生むという営みに恐怖を抱いて生きてきた。
この世界に新しい人間を生み出すのは暴力ではないかと思う。たまに幸せを感じることもあるが、それを考慮してもなお、生きることは苦しいと思うからである。それなのに、ものを感じる主体を新しく生み出してしまって本当に良いのか。なぜ出産が喜ばしいことだとされているのか、ずっとわかっていない。
せめて、生まれる前の子供に「生んでもいいですか」と訊けたらどんなに良いかと思う。わたしも生まれる前に訊かれたかった、訊かれたら「いやだ」と言いたかった。わたしは、できることなら生まれたくなかった。生まれ変わったら何になりたいかと訊かれたときには、「生まれ変わりたくないし、絶対生まれ変わらなきゃいけないなら意識のないものがいい」と答えてきた。
それに自分の周りには、死ぬことを嫌がったり先延ばしにしたがったりする人間が多い。人は今の所かならず死ぬので、現時点では、人を生むということは同時にその人の死をも生み出していることになる。そこで、死にたくないと言っている人間が子供を生んでいるのがどういう理屈なのかよくわからない。自分の子供は死への恐怖を抱いても構わないということなのだろうか。
じっさい、周りの友人は普通に出産をする。しかもそれは祝われており、褒め称えられてさえいる。なぜ? 彼/彼女らはそれぞれの生に満足していて、わたしは自分の生に満足していない、それだけの違いなのだろうか。
そうして生きていたある日、川上未映子『乳と卵』に出会った。少し長いけれど、引用する。
もし、わたしに生理がきたら。それから毎月、それがなくなるまで何十年も股から血がでることになって、それはすごいおそろしい。それは自分でとめられず、家にもナプキンはないし、それを考えるとブルーになる。
もしも生理がきてもお母さんにはいうつもりないし、ぜったいに隠して生きていく。だいたい本の中に初潮を迎えた(←迎えるって勝手にきただけやろ)女の子を主人公にした本があって、読んでみたら、そのなかで、これでわたしもいつかお母さんになれるんだわ、感動、みたいな、お母さん、わたしを生んでくれてありがとう、とか、命のリレーありがとう、みたいなシーンがあって、びっくりしすぎて二度見した。
本のなかではみんな生理をよろこんで、にっこにこでお母さんに相談して、お母さんもにっこにこであなたも一人前の女ね、おめでとう、とか。
じっさにクラスでも家族みんなに報告して、お赤飯たいたとか食べたとかきいたことあるけど、それはすごすぎる。だいたい本に書かれてる生理は、なんかいい感じに書かれすぎてるような気がする。これを読んだ人に、生理をまだしらん人に、生理ってこういうもんやからこう思いなさいよってことのような気がする。
こないだも学校で移動んとき、あれは誰やったか、女に生まれてきたからにはぜったいにいつか子どもを生みたい、と言ってた。たんにあそこから血がでるってことが、女になる、ってことになって、女としていのちを生む、とかでっかい気持ちになれるんはなんでやねん。そして、それがほんまにいいことやってそのまま思えるのは、なんでやろ。わたしはそうは思えんくて、それがこの厭、の原因のような気がしてる。こういう本とかを読まされて、そういうもんやってことに、されてるだけじゃないのか。
わたしは勝手におなかが減ったり、勝手に生理になったりするような体がなんでかここにあって、んでなかに、とじこめられてるって感じる。んで生まれてきたら最後、生きて、ごはんを食べつづけて、お金をかせぎつづけて、生きていかなあかんのは、しんどいことです。お母さんを見ていたら、毎日を働きまくっても毎日しんどく、なんで、と思ってしまう。これいっこだけでも大変なことやのに、そのなかからまたべつの体をだすのは、なんで。そんなことは想像もできひんし、そういうことがほんまにみんな、素晴らしいことやって、自分でちゃんと考えてほんまにそう思ってるんですかね。ひとりでおるとき、これについて考えるとブルーになる。だから、わたしにとっていいことじゃないのはたしかやと思う。
生理がくるってことは受精できるってことで、それは妊娠。妊娠というのは、こんなふうに、食べたり考えたりする人間がふえるということ。そのことを思うと、絶望的な、大げさな気分になってしまう。ぜったいに、子どもなんか生まないとわたしは思う。
これは『乳と卵』の、緑子という11歳の女の子がノートに書いた文章である。わたしは大学生のときにこの部分を読み、それ以来、自分の一番の理解者は緑子だと思うようになった。
生まれ変わったらまたこのクラスに生まれたいね、みたいなことを言ったあの子や、将来子ども何人ほしい? って訊いてきたあの子、それに対して2人がいいなって言ってたあの子、また、将来子どもを産むときに困るからという理由で様々なことを制限してきた母とは違って、緑子だけは自分と同じ世界にいるような気がした。そして、緑子という人物を書いてくれた川上未映子にも信頼に似た感情を覚えるようになった。それからのわたしは、彼女の書く本を全部買った。生まれてきてしまったことが本当につらいと思った夜には、よく彼女の本を開いて、独特のリズムの中を漂ったものだ。
そして時は流れ、2019年、『乳と卵』の続編である『夏物語』が刊行された。もちろんわたしはこれも買って読んだ。
『夏物語』読後の絶望――また、誰もいなくなった
以下は、『夏物語』読後の自分のツイートである。
なんとなく価値観が似ていると思っていた人が、本当ははじめから決定的に違う世界に生きていたんだとわかる瞬間のひとりぼっちな感じ。これはもう破格のつらさで二度と味わいたくないのに、これからも何回もこれを味わうんだろうと思うとしんどすぎて涙でる。せめて女じゃなかったらよかったのかな。
— 𝓼𝓮𝓻𝓪𝓶𝓪𝔂𝓸 (@seramayo) October 5, 2019
簡単に言うと絶望していた。
人を生むことに対してかなり慎重派だった「夏子」(緑子の叔母にあたる人物)が、あまりにも曖昧に思える理由で子どもを生むことを決め、しかもそれが物語全体の結末だったからだ。
帯には「圧倒的感動」と書いてあった。
どこが?(本当に訊きたい。どこが感動ポイントでしたか?)
感想を検索すると「こんなこと考えてみたことなかった〜」みたいなやつがあった、しかも女性の感想。ほんとうに信じられなかった。これを考えずに生きていられる女性にどうやったらなれるのか知りたかった。でもこれを考えなかったからこそ子供が生めたという人がけっこういるのかもしれない。(考えて生んでいる人もたくさんいると思っているけれど)
またもや世界から疎外された気がした。緑子はいなくなってしまった、緑子をあんなふうに書いた人も、もうこの世にはいないのだと思った。
そんな『夏物語』の中にもわたしと近い人物がいて、それは「善百合子」という女性だ。
「ただ、弱いだけなのかもしれないけれど」善百合子は頼りない笑みを浮かべて、そして小さな声で言った。「生まれてきたことを肯定したら、わたしはもう一日も、生きてはいけないから」
わたしにはこの言葉の意味がとてもよくわかる気がした。善百合子を描いてくれたこと自体は心から嬉しかった。
だからこそ、そのあと善百合子に対して夏子が発した言葉や取った行動が本当にほんとうに許せなかった。引用もしたくない。今読み返しても腹が立つ。生むと決めた人独特の傲慢さを煮詰めたような表現だ。(この表現ができるところが、川上未映子の凄さだと思うのだけれど)
今思い返すと可笑しいことだけれど、『夏物語』読了直後のわたしはなんだか川上未映子に裏切られてしまったような気がして、インスタグラムのフォローを衝動的に外したりもした。勝手に信じたり親近感を抱いたりしていたのは自分なんだけどね。でも実際に川上未映子は、『乳と卵』と『夏物語』の間に子どもを生んでいる。この人が子どもを生むことを決めたのも夏子のような曖昧な理由だったらどうしよう、と思ったら本当につらい気持ちになってしまったのだ。
生まれてしまった苦しみを共有できていると思っていた人がいつのまにか子どもを生んで親になることはこれまでにもよくあった。なぜ、あんなに苦しいと言っていた生を新たに生み出そうと思ったのか。その理由を聞いて納得できたことはまだ一度もない(そういうことを訊ける関係性に置いてもらっているのは幸福なことだ)。そしてこういう経験は、これからも何度もあるのだろう。誰も悪くない、とてもつらい経験だ。(そう、たぶんわたしは本当のところでは子どもを生む友人たちを心から理解したいのだし、もっと言えば、自分が生まれてきたことを正当化できる理由が知りたいのだと思う)
自分の中の反出生主義と向き合いたい
『夏物語』を読み終えて数日間は心が重いままだった。この、あまりにも苦しい読書体験を経て、わたしはそろそろ自分の中の思想と向き合わなければならないのかもしれないと思い始めた。
『夏物語』の参考文献には、デイヴィット・ベネタ―の『生まれてこなければ良かった:存在してしまうことの害悪』が挙げられている。ベネターは「反出生主義 anti-natalism」の論客である。反出生主義は、ごく単純に述べると、子どもを生むことに対して否定的な立場を取る思想のことである。
わたしが『夏物語』を読み終えたのは10月初旬のことだが、その頃、奇しくも『現代思想』11月号においてベネターを中心として反出生主義が特集されると知った。
自分の中で「生まれてこなければよかった」「子どもを生むことは悪」という考えが当たり前すぎたので、それと似た思想とされる「反出生主義」についての論考をわざわざ読もうと思ったことは一度もなかった。
でも、ここらへんで一度向き合っておかなければいけない気がした。『夏物語』で動揺してしまったのは、自分の中での確固たる思想というか、思想の根拠みたいなものが揺らいでいる証なのではないかと思ったからだ。そこで、『現代思想』を購入して様々な論者の主張を読むことは、自分の考えを相対化して捉え直す上で有効な手段だと思えた。
ベネターの「他人事感」にイラつく
『現代思想』を読みはじめてすぐに気がついたのは、「ベネター関連の文章には、やたらイライラしてしまう」ということだ。わたしはどちらかというとベネターの思想と近い考えを持っているはずなのに、ベネター本人の主張に、どうしてこんなにイライラするのか。
ベネター自身の主張やそれに対する様々な人の反論を読み進めて気づいたのは、「ベネターの文章やそれを論理的に批判しようとしている人の文章には、なぜか他人事感がある」ということだ。
それは果たしてなぜなのか――最初は、森岡正博が言うように、ベネターの議論が「哲学的なパズル解き」にとどまって、実存的な問題として捉えきれていないからなのかな、と思ったが、それだけでは説明しきれない気がする。
具体的には、(ぜんぜん論理的な説明ができないのだが、)以下のような感想を抱いてしまうのだ。
ベネターに関連する様々なひとの様々な文章を読みながら、「あなたは産めてしまう身体じゃないみたいでいいですね」みたいなことを言ってしまいそうになることが何度かあった。そんな捉え方よくないって思うけど、でも絶望的な断絶を感じてしまったのは確か……
— 𝓼𝓮𝓻𝓪𝓶𝓪𝔂𝓸 (@seramayo) November 9, 2019
なんというか、わたしたち女は生理のたびに、なんでこんなに痛い思いしないといけないのか、出産というのはこの苦しみと引き換えになるほど価値のあるものなのか、ということを少女のときから月イチでずっとずっと考えているというのに、いまさら分析哲学で論理的に示してドヤ顔されてもな、みたいな感じがするのである。
じっさい小手川正二郎は、ベネターの反出生主義が子づくりにおける現実の難しさを誤った方向に逸らしてしまうと指摘している。わたしもそれ自体には賛成できるのだが、この指摘の根拠として述べられている内容はわたしの感覚とはあまり重ならなかった。
『現代思想』をぜんぶ読んでみても、ベネター周辺の議論に感じた「他人事感」の正体や原因はよくわからないままだ。
しかし、このような「他人事感」を抱くと同時に、『夏物語』やそれを著した川上未映子に対する自分の捉え方が変容してきたのがとてもおもしろかった。
『現代思想』の反出生主義特集を読み進めるうちに、読後あんなにわたしをイラつかせた『夏物語』が本当はどれほど当事者的ですぐれたテキストなのかということが浮き彫りになってきた。
— 𝓼𝓮𝓻𝓪𝓶𝓪𝔂𝓸 (@seramayo) November 9, 2019
川上未映子のあの終わらせ方には本当にムカついたけどでもあの物語はぜったいに自分と同じ世界を前提としたものであったのだということ、その事実の優しさが身にしみる。みたいなことを考えるたびに、この生というのはいったいなんなんだ難しすぎる、、となる。
— 𝓼𝓮𝓻𝓪𝓶𝓪𝔂𝓸 (@seramayo) November 9, 2019
全然わからない、けれども
結局『現代思想』を読んでも自分の立場をクリアにすることはできなかった。むしろ、ベネター自身の主張に対してネガティブな感想を抱いてしまったことで、より混乱したような気もする。
しかし、ベネターの反出生主義に対する様々な反論を読むことで、自分の中でけっこう幅をきかせていた反出生主義的な部分に対して、自分で反論を加えることが可能になったことは収穫だった。自分の考えについて、これからもっと深め、広めてゆく価値があるように思えた。
『現代思想』を読んだ中で、今のところ自分が取り入れられそうな考えは、
佐々木閑が仏教的視点から絶対的真理であると述べる以下の考え方
「生きることを苦であると自覚した人にとって子供は、自己をその苦しみの世界に縛り付けるくびきとなるので、作ってはならず、作ったなら捨てねばならない」(つまり、ベネターのように子供のことを考えるのではなく、自己のことを考えた結果としての反出生主義)
または逆卷しとねが紹介している、ダナ・ハラウェイの「非‐出生主義者 non-natalist」的立場
の2つである。
そういえば反出生主義の文脈でベネターと同じくらい有名なのがシオランだと思うが、わたしはシオランにはイラついたことがない。それはなぜなのだろう?
木澤佐登志の述べるところによると、シオランは反出生主義を「ひとつの個人的経験」と捉えているらしく、そこが関係あるのか?(ベネターは割と宇宙的視点に立っている)
シオランに関する議論も勉強してみなければならないと思った。(他の反出生主義者だと、ショーペンハウアーにもちょっとイラついたことがある)
それから、わたしが「子どもをつくること」を一般的に忌避してしまうことに関連して、これまで自分が検討してきたのとはまったく別の視点からヒントを与えてくれそうなのが、古怒田望人が論の中で紹介していたリー・エーデルマンの「子供なるもの the Child」概念だ。
エーデルマンは、逆巻しとねの論においてはハラウェイと並べて論じられていた。
最近なんとなくクィア関連の議論がわたしに新たな糸口をもたらしてくれるかもしれないという気がしていたが、『現代思想』を一通り読んでみてその予感がますます確かなものになってきた感じがする。
そして、いくつか自分自身の認知パターンに気づくことができたのも収穫であった。
まずは島薗進が、ゴータマ・ブッダが自分の誕生と引き換えに母親を喪っていることを引き合いに出して、仏教においては生まれることと害することが結びついているということに言及していた。このブッダの境遇は自分と少し近いので、自分の反出生主義的な考えは、生まれついた環境にも影響されているかもしれないと思った。
さらにベネターの思想について「他人に害悪を与えてはならない」という消極的義務の優先性が前提となっていることを小手川正二郎が指摘している。これは確かにそのとおりかもしれないと思ったし、この消極的義務の優先性が自分の中にも巣食っていることに気がついた。「他人に幸福を与えなければならない」という積極的義務を優先させるという生き方もあるのだ。
現時点でのわたしの考え
ほとんど個人的メモのような記事になってしまったが、現時点でのわたしの考えをまとめて終わろうと思う。
- 自分の思想はベネターとは少し違う気がする(何が違うのかはまだわからない)
- 「出生主義」でも「反出生主義」でもない立場を探りたい
- もっと勉強することが必要である
- 川上未映子のインスタはフォローし直そうと思う
こんな感じかな。
とりあえず今は、みんなの『夏物語』の感想をきいてみたいなあ、と思えるようになった。大きな進歩である。