大フィルの第549回定期。指揮は大山平一郎、ヴァイオリン独奏は金川真弓。
聴き始める前は芥川とショスタコーヴィチを楽しみにしていたが、そのあいだに挟まれたブラームスのヴァイオリン協奏曲が本当に凄まじく、わたしにとっては本日のメインとなった。
実は今まで、何回聴いてもこの協奏曲の意味がわからなかった。でも今日の金川さんの演奏で完全に腑に落ちた、落ちてしまった。
同じ楽譜を演奏しているはずなのに不思議だ。こういうことがあると、クラシック音楽を演奏するという行為はすごいことなんだと思う。解釈という行為の重み。何度も、少しずつ違うやりかたで繰り返すことの力……。その一部として関われていること、嬉しいような怖いような感じがある。
1楽章。これまでは乾いたペン先が皮膚にひっかかるような違和感を抱いてばかりいたのに、今日はものすごい染み渡り方だった。この感情、ずっと前から知っていた……懐かしさのあまり泣きそうになってしまう。体温と同じ温度のお湯にひたって、何の心配もなく浮かんでいるようだった。皮膚表面は境界としての役割を捨て、ホールじゅうにひろがる美しい深緑のインクが、体内に何の痛みもなく染み込んでくる。そのまま2楽章の時間のなかへと、自分自身が拡大する。そして3楽章で目が開く。この曲はこんなにも刺激的だったのか。
どんな言葉でも言い尽くせないような感覚、表す手段がまさにこの曲しかない……と思った。これが非言語の芸術なんだな。その芸術性っていうのが作品そのものだけでは達成し得ない、というのを考えるとなんだか、人間そのものとか、その内部の神経などの構造とか、宇宙とか、あらゆるもののスケールが実感されて寒気がする。
感染症の影響で、指揮者もソリストも変更になったうえでの、この演奏。もともとの出演者もすごく楽しみにしていたので、変更を知ったときは残念だったけれど、そのおかげでこの演奏が聴けて本当にラッキーだった。
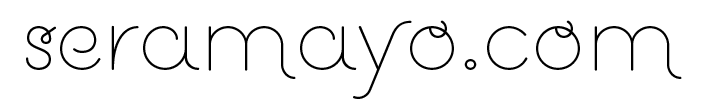
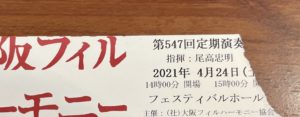

コメント