今年のクリスマスは本当にやる気がなくて、ディナーを作る日の朝もめちゃくちゃゆっくり起きたり、せっかく起きて朝食をとった後もすぐに炬燵に飲み込まれて更に長時間意識が消失したりと散々だった。
なぜこんなにも気持ちが乗らなかったのか、今でもよくわからない。昨年のクリスマスはきちんと気合いが入っていた記憶がある。一週間前くらいから作りたいレシピを印刷、メイン料理にも煮込みを設定したので料理をしている時間はかなり長かった。そのような諸々を思い返すととにかく気が重かった、同じことはとてもできない気がした。
昨年の日記を読み返すとそこにいる自分はあまりにも幸福感に包まれていてまるで共感を抱けず、そういうつまらぬ現在の自分自身にも幻滅、2017年にも2018年にも自分の好きな自分が生きていないみたいで、とにかくそのことについて考えるのをやめたい、という気持ちで炬燵に潜り込んだのはディナー当日の、ほとんど昼に近い朝であった。
先程は少し残っていた朝の空気がもうほとんど昼に染まってきた頃に目を覚ましたら、なんとすでに、夫の手によってスープが完成しているらしく気持ちはもっと焦る。前日から試作を重ね、当日更にバージョンアップして完成させるその計画力と実行力を前に、訳が分からなくなる。そのときわたしの気持ちはどこにいたのかというと、あの幸福な光に包まれていた2017年のクリスマスと、何もかも灰色でざらざらしているような2018年のクリスマスとの間、そのちょうど半分、おそらくは2017年6月頃の、存在しない日付の寝苦しい夜に落ちていた。
もうこのままわたしは戻れない。昨年も一昨年も、いつもやっていたことをできないままでクリスマスが終わり、人生もまたこのようであるのだろうか。
そう思っていたとき、じめじめした暗がりに突如として光が差し込む。わたしの座り込む夜の底の遥か頭上にある、カレンダーの罫線のあたりからめり込んでくる、銀色のゆるいカーブ。その上には、たまごとミルクを混ぜたような優しい色の液体がゆらめいていて、やがてとろとろと、わたしの全身に降りかかった。生命の象徴のようなその黃色は、わたしの身体だけではなく、無限に続くと思われた夜の底一面に広がってゆき、頭上から差し込む銀色とそれに反射する光がその様子を照らし、そうして夜が夜でなくなり、ついにわたしの実際が明るみに出されたのだ。
スプーン一杯の味見に、こんなに救われることがあるとは。全身を満たす味。それは不思議と、口内から染み渡るというより、皮膚の外側からもたらされる心地よい充足感であった。わたしは食べているのか、それとも食べられているのかよくわからなくなるくらいに、包まれる思いがした。食べるっていったい何なのだろう。人を救う料理というのは本当にあるのだ――と思った。
白ワインでできたそのスープが、今回のクリスマスの主役であったと思う。それを味見したあと、とりあえずスーパーマーケットに行ってみたらうつくしい丸鶏を発見、ずっと作ってみたかったけれどなんとなくチャレンジせずにいた丸々一羽のローストチキンを今年ついに作ることができた。前菜はエビを買ってきて茹でてカクテルにしたり、野菜とタルタル風にしたり、シンプルだけれどいい感じだった。近くにあるフレンチレストランが手がけるケーキも、ずっと食べてみたかったのをようやく買うことができて、予想していた以上に美味しくて、嬉しかった。用意していたワインはすべて幸せな芳香を放ち、ろうそくの静かな炎に照らされて、まるで液体の宝石であった。
何もかもが救われて、ほんとうの夜が来た。れっきとした2018年12月24日の夜に、わたしはいた。
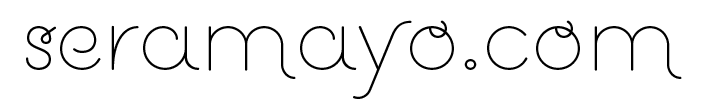






コメント
コメント一覧 (1件)
[…] Christmas dinner 2018 2018.12.27 […]